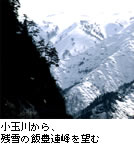



雪解けが進み、やがて春が訪れようとしている。ブナいきりと称して、居ても立ってもいられないほど暖かい日があると、その翌日からきまって、ブナの森はいっせいに芽を吹きはじめる。ブナの青葉が日ごとに若い緑を加えてゆく。暦の春からはずっと遅れて、雪国の春はそうして、騒ぎ立つブナの森のかたわらで幕を開ける。
野山はまさに山菜の宝庫となる。春一番が吹く頃には、アザミやフキノトウが顔を出す。それから梅雨の頃にかけて、ゼンマイ・アイコ・ミズ・ウルイなどが次々と採れる。ゼンマイ採りが終われば、本腰入れて田んぼ仕事にとりかからねばならない。苗代作りやサツキ(田植え)の準備など、忙しい日々が続いてゆく。そんな季節に、小玉川では昔から、春のシシ山(熊狩り)が行なわれてきた。
狩人をマタギと呼ぶようになったのは、最近のことだ。小玉川あたりでは、狩人や山子(ヤマゴ)、あるいは鉄砲打(ぶ)ちと称してきた。古くは、暮らしの糧を得るために行なわれた狩猟も、いまはいくらか様変わりしている。明治の半ば頃までは、まだ手槍や火縄銃で熊を仕留めていた、という。やがて村田銃が広まり、それもいつしか、ライフル銃の時代へと移り変わってきた。
春のシシ山は、雪の消え残る山野を舞台にくり広げられる、勇壮な春の祭りにも似ている。男衆の血が騒ぐ。狩人の男らはみな、鉄砲を肩にかけ、ナメ棒を携えた姿で集まってくる。山の神の宿りする木に手を合わせ、安全と豊猟を祈願する。そして、雪原に熊を求めて、山の懐深くへと分け入ってゆく。
十人から二十人ほどの鉄砲打ちによる巻狩りである。山を誰よりも知る狩人がムカダテとなる。そのムカダテの指揮と統制のもとに、ナリコミ(勢子)が多人数で巻いて、少しずつ熊を追いつめ、最後は、鉄砲でしめる。しめるとは仕留めるの意だ。トランシーバーとライフル銃、そして猟友会の時代にはなったが、春のシシ山はいまも、こうした巻狩りの形式で行なわれている。かつては、山中の小屋に泊りがけの狩りもあった。
熊をしめると、山や沢ごとにサナデル(解体)場所があり、そこへ運んだ。手慣れた人がコガイ(小刀)で解体する。毛皮と脂を切り離し、熊の胆(い)を取り出してから、ホナ(心臓)とパッケ(頭骨)を沢の上(かみ)のほうに向けて供える。ムカダテが山の神に感謝を捧げ、拍手を打つと、ほかの狩人らはみな頭を下げる。それから、解体した熊を分けて背負い、里まで運び降ろすのである。
獲物は参加した者らが平等に分配する。熊の胆は薬として珍重され、金と同じほど、高値で取り引きされた。毛皮もかつては高く売れた。肉は分けて食べる。骨は膏薬になる。無駄なところは何ひとつない。熊はまさに、山の神からの大切な授かり物であった。
ほかにも、熊狩りにはいくつかの形式があった。雪解けがはじまる頃には、冬眠から覚める熊を狙って、穴見が行なわれた。木の洞や岩穴などに身をひめる熊を、棒で突いたり松明でいぶし、外に誘い出してしめる。いまは禁止されているが、秋は罠猟の季節であった。シシミチという熊の通り道に、木を組み、石を乗せた罠の落トシを作った。オソとかヒラと呼ばれた。小玉川では、熊穴は部落持ちであったが、オソ場の権利は数人が組んで所有していたらしい。土地によって、これらの権利関係は異なっている。
山の神は女神と信じられている。それゆえ、山の神が支配する山のなかは、女人禁制であった。山には厳しい掟があり、タブーがあった。女の話はするな、唄を歌うな、ほそぶき(口笛)を吹くな、といったタブーのなかには、いまも守られているものが多い。サナデル(解体)・サキノッタ(死んだ)・マカ(血)・ホナ(心臓)・パッケ(頭骨)など、山のなかだけで使う、特殊な山言葉もまた、少なからず受け継がれている。
山の神神社は六斗沢にある。小玉川の総社であり、十二山の神とも十二神とも呼ばれている。十二は聖なる数と信じられ、十二人で山に入ることはタブーとされてきた。あたりは樹齢が二、三百年はある杉の大樹に囲まれている。社殿のなかには、オコゼが祀られてある。山の神は醜い女の神様だ、おまけに、とても嫉妬深いらしい。だから、姿がひどく醜いオコゼ魚を供えると喜ぶ、という。そんなオコゼ奉納の由来が語られる。山の神とオコゼの伝承そのものは、とりたてて珍しいものではないが、オコゼを現実に祀る姿を見ると、やはり不思議な気分になる。ともあれ、小玉川の狩人たちは昔から、狩りの獲物が豊かであるようにと、オコゼを供え物にして祈願してきたのである。
春のシシ山が終わると、熊祭りが催される。祭りの日は年ごとに変わった。十数年前までは、片貝にいた法印(山伏)が祭りを主催していた。さらに古くは、山祭りと称され、家のなかで執り行なわれた。左右に五色の梵天が二本立てられるだけの、簡素な祭壇が作られた、という。
いまは、五月の連休に熊祭りを行なっている。祭りの場も屋外に移された。梅花皮(かいらぎ)荘の前の広場で行なわれる。祭壇には十二本の梵天が立てられ、熊の毛皮や剥製が飾られる。昔はなかった、と年寄りの狩人はいう。たくさんの観光客が熊祭りを見物するために、この季節になると、小玉川を訪れるようになった。
とはいえ、法印の時代には、昔からの作法で熊祭りは行なわれていたらしい。ヤグラを組み、紙の御幣を立て、法印が祝詞(のりと)と経を唱えながら、煮立った釜の湯を笹の葉でかき混ぜる。法印は呪的な力によって、その湯を清水に返し、それを上半身裸の若い狩人二人に振りかける。熊祭りの中心は、このお湯立ての儀式だったのである。穢れを浄化するための、修験道的な色合いの濃い行事であった。
熊祭りはいわば、しめた熊の霊をあの世に送って、鎮魂と供養を行ない、また、狩りの季節をつつがなく終え、豊かな獲物を授けてくれた山の神にたいして、深い感謝と祈りを捧げる神事だった。狩人たちは熊をしめたとき、山中で解体してから、十字を入れた心臓や頭骨を供えて、山の神にたいする感謝の祭りを行なう。そうした古風な、狩人たちの山の神信仰のうえに、修験道が覆いかぶさったのであろうか。法印と呼ばれる人々は、中世以降のいつの時代にか、あらたに山祭りや熊祭りを創った。そして、鎮魂の祭りの演出家として、山の村々の狩猟文化に関わってきたのである。
山形はもっとも豊かなブナの森を抱えた県である。しかし、驚くほどに、その事実は知られていない。世界遺産に登録された白神山地に劣らぬ、ブナの原生林が見られる、ともいう。このブナの森はいまや、「自然保護」のシンボルにまで祭り上げられた感がある。その行き過ぎや歪みは措くとしても、それが山形にとって、大切な地域資源であることは否定しがたい。そして、その地域資源であるはずのブナの森は、小国町の「白い森構想」などを除いては、ほとんど活用の道が探られていない。宣伝下手な県民性が顕われている。
ブナの森をたんなる「美しい景観」として売りに出すことには、抵抗があるし、問題もまた多い。情緒的な、ファッション感覚の「自然保護」の流れに掉さすためにも、新しいブナの森のイメージを打ち出す必要がある。それはたとえば、眺められる自然ではなく、縄文以来のはるかな時間のなかで育まれてきた、もうひとつの自然のイメージである。人と自然とが、微妙な折り合いをつけながら共生・共存してきた、暮らしとなりわいの場としてのブナの森こそが、これからは語られる時代となる。その意味では、山形はまさに、絶好の条件を満たしうる土地と言っていい。ブナの森を舞台とした、狩猟と採集にかかわる数千年の伝統があり、山の幸・川の幸に支えられる暮らしの形を留めた、山あいの村々が生き残っているからだ。そこに残された、人と自然とが共生してゆくための知恵・技術・世界観などを掘り起こしつつ、ブナの森を「自然に触れ、自然に学び、自然を語り合う場」として位置付けなおすことが、あらたな課題として浮上しつつある。
(2)熊祭りについて
熊狩りや熊祭りは、一部の情緒的な「自然保護」を唱える人々によって、野生の獣を殺す「残酷なショー」のごとくに語られてきた。しかし、現実は大きく異なっている。狩人やマタギほど、深く自然を知る人々はいない。山に暮らす人々は、たしかに山の領域を侵してきた。かれらは木を伐り、獣を狩り、山から多くのものを奪う。森の獣や川の魚、山菜・キノコ・木の実など、豊かな山の幸・川の幸を命の糧としてきたからである。そして、それゆえに、ある限度を超えて自然を侵すことは、けっしてない。そこには、人と自然とが微妙な折り合いを付けながら、共生と共存を果たしてゆくための、知恵や技術が伝統的に存在した。だからこそ、マタギのような山に暮らす人々は、誰よりも深く自然を知っていたのである。
むしろ、狩人や狩猟文化は、これからの時代の「自然保護」の形を考える場合、大切な地域資源として見直されねばならない。県内全域において、山村を中心とした地域の狩猟の民俗を調査し、把握しておく必要がある。それはやがて、山形の原風景の一端をになうものとして再評価される。思えば、狩猟文化もまた、縄文以来の東北の基層文化を照らし出す拠りどころである。日本列島の東と西の文化的な差異が、そこにとても見えやすい形で露出していることも、見逃すことはできない。熊祭りを「残酷なショー」と見なす人々には、自然を「守る」ことはできない。
![]()
![]()
![]()
![]()